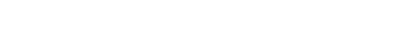当協会地域ダンス・ムーブメントセラピー推進委員会の助成により、ワークショップが二件開催されましたので、報告いたします。
①
タイトル :発育発達と動きの関係性を学ぶ
講 師 :神宮京子
日時・場所:2014年1月25日、岡山
②
タイトル :個とグループの関係 パート2
講 師 :荒川香代子
日時・場所:2014年3月16日、大阪
特別ワーク 「発育発達と動きの関係性を学ぶ」を開催して
ダンスセラピー/ワーキンググループ”プロセス” 山下弥生
私たちダンスセラピー/ワーキンググループ”プロセス”では、自分たちが講師を務める通常ワークとは別に、2010年より荒川香代子氏を講師に迎え、岡山・広島・大阪で特別ワークを企画し、メンバーの研修ともに一般対象にダンス/ムーブメントセラピー( 以下DMTと略す )の体験と広報を目指して活動を行ってきた。その際にメンバーはワークの企画に留まらず、一参加者としてワークを体験し、ワークの終了後にはメンバーのみのアフターミーティングも行って、ワークの検証とセラピストロールに関する学びも積み重ねている。


今回は「発育発達と動きの関係性」をテーマに、メンバーの学びを深めることはもちろん、DMTから見た子どもの動きの理解について、地域の保育や教育関係者とともに学ぼうと考えた。メンバーは発育発達に関して荒川氏の主催する養成講座で学んでいるが、メンバーが揃って同じワークを体験することや、新しい参加者との体験の共有すること、さらには同じテーマであってもセラピストが変わることで学びあえるものが広がってくるという、体験による学びの可能性に期待し、神宮京子氏の発育発達のムーブメントに関するワークを岡山で開催すると決定した、ここで協会の地域活動助成事業により、初の助成金を獲得できたことは、私たちの企画を大きく前進させることとなった。
さて1月25日は岡山には珍しい時折雨が混じる曇天であったが、午後2時きっかりに始まったワークは、あっという間に3時間が過ぎ、メンバーはもちろん初めてDMT体験された参加者にとっても自分主体で無理のない学びの時間を過ごせたと感じた。
ワークは、ケッセンバーグの運動分析( 以下KMPと略す )を簡単に紹介いただいた後、今の自分の動きについて、他者との動きの交流と、それを動きの発育発達の視点から捉えることとで検証しながら進んでいった。発育発達の動きとは今すでに大人である私たち自身の動きに、まぎれもなく存在している動きの個性と言えるのかもしれないが、その動きを丸ごと認めて他者と踊りあう中でエネルギーを発揮し、より私らしいあり方として姿勢や言葉にも表われてきた。それらは各自のワークの流れに乗って自然発生したものであり、セラピストと深い洞察に支えられた見守りと、参加者の対等で真摯な学びあいから育ったものと思われた。
参加者のアンケートでは、初めての方も安心して豊かな時間を過ごせたことがわかり、企画したメンバーも充実したワークに達成感を得られた。なおプロセスでは普段は日曜日にワークを開催することが多く、今回のように土曜の午後に開催した影響について、参加者からは特にコメントはなかったが、開催曜日や時間の設定には工夫の余地もあったかもしれない。特に寒さの厳しい1月末の開催であったため体調不良による欠席もあり、更に受験シーズンと重なったことで参加をためらう方もおられるなど、ワークの開催時期については検討が必要であることも教えられた。ワークは継続してこそ、参加者の気づきを促す可能性が増すと思われ、今後も協会の助成金を得て、定期的にワークを企画できることを望んでいる。
特別ワーク 「個とグループの関係 パート2」を開催して
Petit Pas 淡野 登志
私はダンスセラピー/ワーキンググループ”プロセス”での体験を経て、神宮 京子氏のダンスセラピー講座を受講した後、Petit Pasを昨年立ち上げ、一般対象にダンス/ムーブメントセラピー( 以下DMTと略す )の体験と広報を目指して活動を行っている。今回はダンスセラピー/ワーキンググループ”プロセス”と共同で荒川香代子氏を講師に迎え、大阪で特別ワークを企画した。
ワークは「個とグループの関係 パート2」というテーマで、個人がグループと関わりながら、いかに成長していけるのかに焦点をあてて、体験しながらの学びを深めようというものである。
協会の地域活動助成事業により、助成金を獲得できたことで、ワークの実現を大きく後押しすることができた。
ワークに際して、講師の荒川氏より、以下のレジメを配布された。
『ダンス/ムーブメントセラピーでは、身体表現を通して個人が環境や人間関係においてどのように適応し、内的なこころの欲求や願望との関係をどう図っているのか、これらの関係性・・・すなわち外的なもの(現実的な面)と内的なもの(心の中)とのギャップをどうとらえ、本人がどのように体験しているかに重点を置きます。
「感情の器(うつわ)」として自分のからだが、他者との出会いでどのような対話が始まり、どこに進んでいくか・・・、そこには根源的な乳児と養育者との「共振」(ダンスとも言えます)と情緒的なわかち合いの体験と結びついてきます。養育者によって「感じることを感じるように」、私たちは他者との関係のなかで、実感し学び、わかち合い、個性と愛情を築き上げていきます。
これは一つの過程ですが、私たちは人によって喜びや楽しさも経験し、また人によって傷つけられ、自信を損なわれる等悲しい思いもします。今回は「情動調律」をキーワードとし、からだに響きわたる感情の音色に心を留め、そこにダンス/ムーブメントを使ってその時のメロディーを奏でていければと考えます。』
参加者は7名と募集人数に届かなかったが、ダンス/ムーブメントセラピーを繰り返し体験している人たちが集まったことで、動きや言葉で共有することへの抵抗が少なく、いろいろな人と踊りあう中で銘々が大切にされながら、体験を広げたり深めることが実感できた。途中2度ほど休憩をはさんだが、流れが途切れることはなく、4時間のワークを堪能することができた。そこには今回のキーワードである情動調律しながら、共振する参加者が確かに存在したといえよう。

企画側も充実したワークに達成感を得られた。今回は企画も助成の決定も開催直前となり、インターネットによる告示も遅れたことによって、参加者は少なく、特に年度末の日程設定や広報には工夫が必要と考えられた。その一方で参加者にはじっくりと深いやり取りが可能となって、贅沢な時間を楽しむことが出来た。
ワークは継続してこそ、参加者の気づきを促し。グループを成長させられると思われ、今後も協会の助成金を得てワークを企画していきたいと考えている。
(JADTA News 111より)